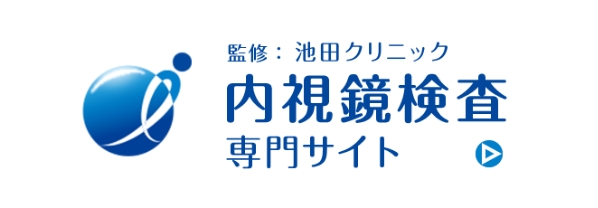- TOP
- メタボリックシンドローム
内臓脂肪に潜むリスク
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積(内臓脂肪型肥満)を背景に、高血圧・高血糖・脂質異常などの生活習慣病の危険因子が複数重なった状態を指します。これらの因子はそれぞれが独立して健康へのリスクとなりますが、複数が同時に存在すると、動脈硬化を急速に進行させ、心筋梗塞や脳卒中、腎不全といった深刻な疾患を引き起こすリスクが飛躍的に高まります。
近年、特に40代から60代の働き盛りの世代に増加しており、日々のストレスや不規則な生活リズム、運動不足、食生活の偏りといった背景が影響しています。「少し太ったかな」「健康診断で再検査になった」というような軽微な自覚から始まり、症状がないまま進行するのが特徴です。
メタボリックドミノとは?
「メタボリックドミノ」とは、内臓脂肪型肥満を起点として、高血糖・高血圧・脂質異常といった危険因子が次々と連鎖的に発生し、最終的には動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、腎不全へと進行していく様をドミノ倒しに例えた概念です。この連鎖を途中で食い止めるためには、最初のドミノである内臓脂肪の蓄積を早期に見つけ、生活習慣の見直しを行うことが非常に重要です。
診断基準について
日本では、以下の基準に基づいてメタボリックシンドロームの診断が行われます。
| 腹囲(へそ周囲径) | 男性85cm以上、 女性90cm以上 |
|---|
以下のうち2項目以上を満たす
- 中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満
- 収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
- 空腹時血糖110mg/dL以上
この基準に一つでも該当する方は、生活習慣の見直しや医療的介入による予防が求められます。
当院での対応
池田クリニックでは、内臓脂肪や血圧・血糖・脂質の評価を通じて、総合的にメタボリックシンドロームのリスクを判定しています。腹部エコーを活用した脂肪の蓄積評価、血液検査での中性脂肪・HDLコレステロール・血糖値の測定、尿検査による腎機能のチェックなど、多角的な検査を行います。
迅速検査機器を導入しており、HbA1cや血糖値は当日のうちに結果がわかります。これにより、検査から指導・治療方針の決定までをスムーズに行うことが可能です。必要に応じて、管理栄養士による食事指導、看護師による運動習慣改善のアドバイス、医師による薬物療法を組み合わせた包括的な治療計画を提案しています。
このような方は注意が必要
- お腹まわりが年々気になってきた
- 健診で「脂肪肝」や「高血圧」「高血糖」を指摘された
- 家族に糖尿病や心臓病の既往がある
- 食後に強い眠気やだるさを感じる
- 運動をほとんどしない生活が続いている
- 外食が多く、野菜不足や炭水化物の過剰摂取が気になる
こうした状況は、すでにメタボリックシンドローム予備群である可能性があります。
生活習慣の改善でリスクを軽減
メタボリックシンドロームは、生活習慣の改善によって十分に予防・改善できる病態です。
以下の5つのポイントを意識することが基本となります。
- バランスの良い食事(脂質・糖質・塩分の取りすぎに注意)
- 毎日30分程度の軽い運動(ウォーキングなど)
- 質の良い睡眠と十分な休養
- 禁煙と節度ある飲酒
- ストレスの適切なコントロール
当院では患者様の生活環境や仕事、家族構成なども考慮したうえで、無理なく取り組める改善策をご提案しています。
検査内容例
腹囲・体重・BMIの測定
体格や肥満度を客観的に評価し、内臓脂肪の蓄積を推測する指標となります。
血圧測定
高血圧の有無を確認し、動脈硬化や心血管リスクの早期発見に役立ちます。
血液検査(中性脂肪・HDLコレステロール・血糖・HbA1cなど)
脂質や糖代謝の状態を把握し、メタボリックシンドロームの診断と管理に不可欠です。
尿検査(腎機能評価)
糖や蛋白、腎機能の指標を確認し、生活習慣病による合併症の兆候を捉えます。
腹部エコー(脂肪肝や内臓脂肪の評価)
非侵襲的に肝臓や内臓の状態を確認し、脂肪肝や内臓脂肪の蓄積を視覚的に評価できます。
迅速HbA1c・血糖測定(即日結果対応)
その場で血糖コントロールの状態を確認でき、迅速な対応が可能です。
メタボかも?と思ったら
特定健診で「要再検査」や「生活習慣改善の指導が必要」とされた方、過去に指摘を受けたまま対処していない方も、ぜひ一度ご相談ください。ご自身の健康状態を正しく知り、未来の病気を防ぐ第一歩を踏み出しましょう。